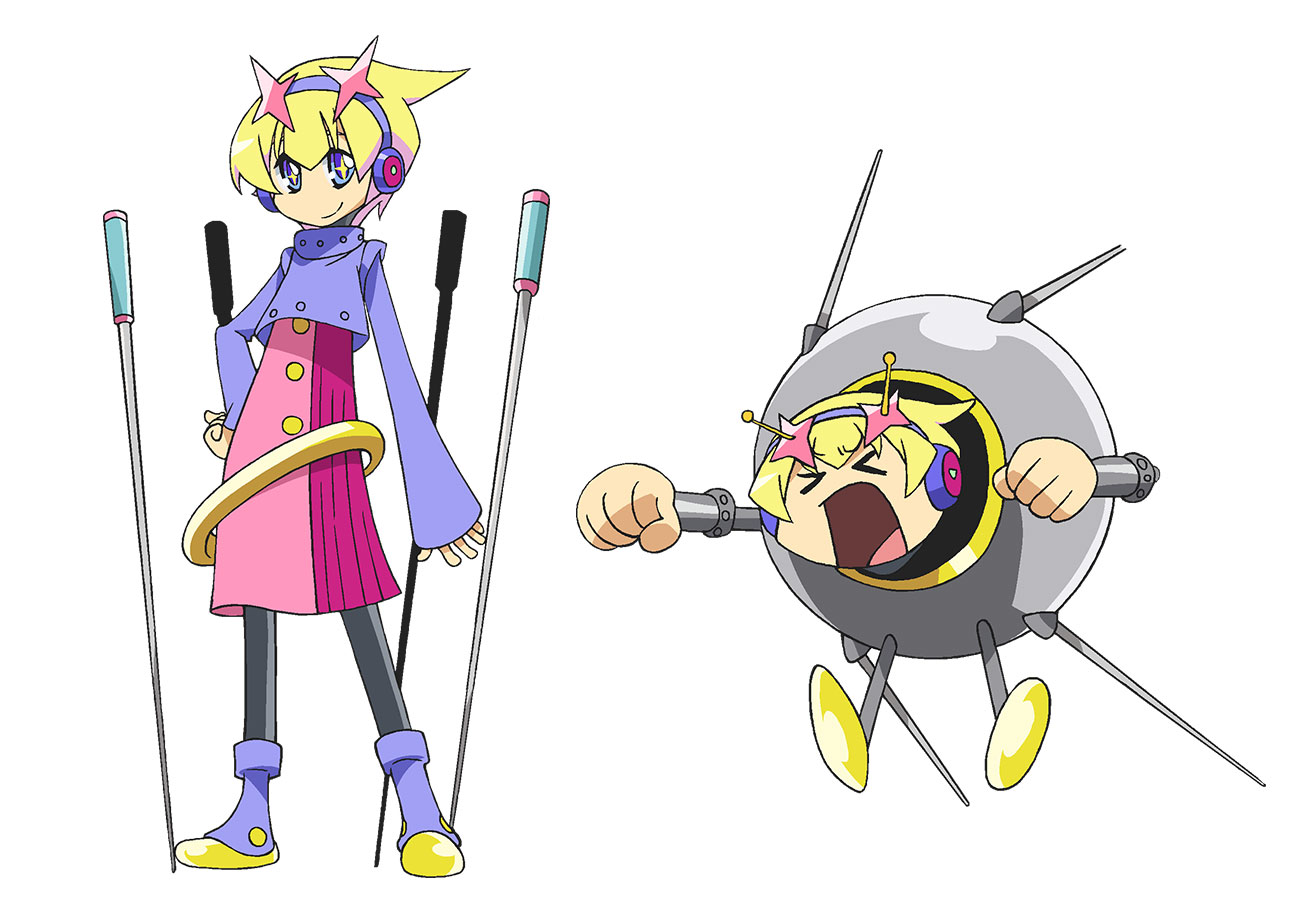20 November. 2015
コラム「超人探訪記」第7回「宇宙と電気と人と……」
文:氷川竜介(アニメ特撮研究家)
以前述べた「宇宙ブーム」の原点は、第二次世界大戦の終戦から12年後の1957年。当時のソビエト連邦が人工衛星スプートニク1号を打ち上げ、米ソ宇宙開発競争が本格化した。両国とも使用したロケットは相手国を撃滅させる弾道ミサイルの技術転用であるから、冷戦終結まで科学には平和と戦争の二面性が常に秘められていたわけだ。そんな時代性の影響下にあった児童ものでは「ロケットとロボット」が未来を投影したあこがれの的となる。『ウルトラマン』(66)の主役デザインにもどこか両方のイメージが反映されているし、同時期に始まった手塚治虫原作のTV特撮『マグマ大使』(66)の主役は地球の守護神アース様の作ったロケット人間という設定である。
そして1960年代の日本は、ロボットやロケットが身近と感じられるほどには科学の成果が生活に反映されていなかった。さまざまな表示器も針のある機械式メーターが大半で、LEDによる電気式デジタル表示器よりアナログが主流なのだ。手塚治虫原作のTVアニメ『鉄腕アトム』(63)にしても、随所に人に近いアナログ的要素が入っている。アトムが歩くときには「チュッピ、チュッピ」と足音が聞こえる。この独特の効果音は、サウンドデザイナー大野松雄が楽器のマリンバを6ミリテープに収録、手でリールを回転させてヘッドをこすって立ち上がりを加工したもので、電子音、デジタル音ベースではない。
こうして機械に人間味が入っている一方、人間それ自体が科学の影響で変形・変身するという、子どもにとっては恐怖の極みとなる描写も世にあふれていた。原点はH.G.ウエルズが1897年に発表した小説『透明人間』にあるが、この発想が宇宙時代の特殊撮影によって再生、急速進化した。『美女と液体人間』(58)、『電送人間』(60)、『ガス人間第一号』(60)と特撮の神様・円谷英二と東宝は、特撮映画の可能性を怪獣だけでなく、「変形人間」にも見いだしていた。深読みが過ぎるかもしれないが、「水道・電気・ガス」と都市インフラがモチーフなのは意味深だ。
人でない者が人に近づき、人が人でない状態に変化する。発達した科学技術で都市インフラが豊かになるのと反比例して、人間性はむしろ損なわれつつあるのではないか。そんな漠たる恐怖心が大衆の中に芽生えたからこそ、映画・TVはその不安を映像で鏡のように突きつけ、夢のような物語を語ったのかもしれない。そんな走馬燈のような印象を、第7話は喚起するのである……。